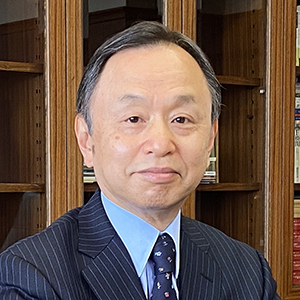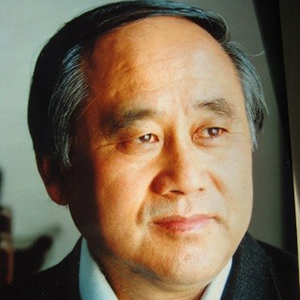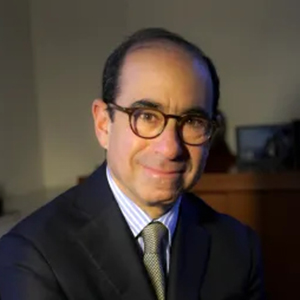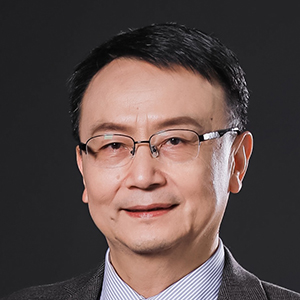第4回 東京グローバル・ダイアログ プログラム
2023年2月20日(月)〜21日(火) 開催
2/20 Mon
| 18:00-19:00 | オープニング開会の辞
ご挨拶
ご講演
|
|---|
| 19:15-21:00 | 『戦略年次報告2022』に関するラウンドテーブルロシアのウクライナ侵略により欧州の安全保障秩序は根底から覆され、「ポスト冷戦」時代は終わりを迎えた。インド太平洋地域では、米中間の緊張が2022年には特に台湾を巡って高まり、近い将来の大幅な緊張緩和は見通せない。ロシアと中国は結束を強め、西側諸国との間で民主主義対権威主義の対峙、あるいは「新たな冷戦」とも呼ばれる世界のブロック化が生じつつある。多国間の枠組みを通じた国際協力は危機に陥り、食糧やエネルギー危機の影響を最も強く受けるグローバル・サウスの国々は、不安定化する国際秩序の中での国益の確保という課題に直面している。こうした中で、日本は国家安全保障戦略を見直し、防衛力の強化を打ち出した。
米国主導の国際秩序の行方と日本の対応を考える上で前提となる現在の国際情勢について、『戦略年次報告2022』の紹介に続き、大局的観点から議論する。 【スピーカー】
紹介文
紹介文
紹介文
紹介文
紹介文
【モデレーター】
紹介文
|
|---|
2/21 Tue
【パート1】米中競争とインド太平洋
| 9:00-10:30 | (1) 政治・安全保障競争と対立が続く米中関係は、2022年には特に台湾を巡って緊張の度合いを高め、根本的な緊張緩和の見通しは立っていない。中国は軍事力・影響力の拡大を続け、米国は中国を戦略的に最も重要な競争相手と見なす一方、米中関係をマネージしようとしている。米中両国はASEAN諸国や太平洋島しょ国を巡ってもしのぎ合い、北朝鮮はミサイル開発を加速化させて地域と国際社会への脅威を一層高めている。
インド太平洋地域における米中の外交・安全保障戦略、米中関係と地域の安全保障の将来、地域諸国の見方と日本を含む各国の政策について議論する。 【スピーカー】
紹介文
紹介文
紹介文
紹介文
紹介文
【モデレーター】
紹介文
|
|---|
| 10:45-12:15 | (2) 経済国際的経済相互依存を基にしたグローバリゼーションは、特にインド太平洋地域でコロナ禍や米中競争の激化の影響を受けて見直しを迫られている。各国は、サプライチェーン強靭化を通じた重要物資の安定供給の確保の取り組みや、先端技術に関する同盟国やパートナーとの連携を進めている。一方で、地域の発展には引き続き自由で開かれた貿易体制と経済相互依存が必要となる。
経済安全保障をめぐる米中のせめぎ合いがインド太平洋地域の経済・貿易体制に与えている影響とその見通し、日本を含む各国の政策を議論する。 【スピーカー】
紹介文
紹介文
紹介文
紹介文
紹介文
【モデレーター】
紹介文
|
|---|
| 12:30-13:30 | 特別セッション 日本周辺の海洋安全保障2022年8月に中国が台湾周辺で行った演習では、ミサイルが日本の排他的経済水域や沖縄県与那国島から遠くない地点にも着弾した。尖閣諸島周辺海域での中国の挑発の度合いは年々増加してきており、近年では日本周辺での中ロ両軍の連携の深まりも確認されている。
こうした中で日本が打ち出した防衛力及び海上保安能力の強化に向けた政策への評価と今後の課題について、日本周辺の海洋安全保障の現状と見通しを踏まえて議論する。 【スピーカー】
紹介文
紹介文
紹介文
【モデレーター】
紹介文
|
|---|
【パート2】ウクライナ紛争の衝撃
| 15:00-16:30 | (1) 政治・安全保障ロシアのウクライナ侵略により欧州の安全保障秩序は根底から覆され、核の恫喝は、核兵器が使用される可能性への懸念を国際社会にもたらした。日本を含む西側諸国は、力による現状変更を許さないとの原則を守る決意の下で前例のない対ロ経済制裁や対ウクライナ支援を実施し、自国の安全保障政策を転換した国も多い。しかし、戦争終結への道筋が見えない中で、西側諸国の対ウクライナ支援の持続可能性と民主主義の強靭性も試されている。
ウクライナ戦争が欧州と世界の安全保障に与えた衝撃、戦争の見通し、欧州における安全保障の将来と各国の政策について議論する。 【スピーカー】
紹介文
紹介文
紹介文
紹介文
紹介文
紹介文
【モデレーター】
紹介文
|
|---|
| 16:45-18:15 | (2) 経済ロシアのウクライナ侵略はエネルギー・食糧などの資源の世界的な供給不安と価格高騰をもたらした。ロシア・ウクライナに穀物輸入を依存してきた中東・アフリカ地域をはじめ、グローバル・サウスの国々は特に大きな影響を受けており、各国の内政や世界経済の将来にも暗い影を落としている。EUはエネルギー・食糧価格の高騰、貿易赤字、ユーロ安、ガス危機に直面する中で、グリーン・トランジションを加速しようとしている。
ウクライナ戦争の国際経済への影響と今後の見通し、国際機関と各国・地域の対応について、食糧とエネルギーに焦点を当てて議論する。 【スピーカー】
紹介文
紹介文
紹介文
紹介文
紹介文
【モデレーター】
紹介文
|
|---|
【パート3】米国主導の国際秩序の行方
| 18:30-20:00 | 米国主導の国際秩序の行方「ポスト冷戦」時代が終わりを迎え、安定的な国際秩序の継続はもはや当然とは言えず、各国は不透明な国際情勢の中で自国の平和と国益の確保という課題に直面している。多国間協力は危機に陥り、核兵器が使用される可能性への懸念も増している。食糧やエネルギー危機は、グローバル・サウスをはじめとする各国の経済成長に暗い影を投げかけている。「新たな冷戦」とも呼ばれる世界のブロック化が生じつつある中で、「ポスト冷戦」時代を象徴した米国主導の国際秩序はどこに向かうのか。ルールに基づく自由で開かれた国際秩序は持続可能か。
国際情勢の現状と見通しを踏まえ、米国主導の国際秩序の行方と、安全保障政策を大きく転換させた日本の対応、2023年のG7議長国としての日本の役割について、大局的観点から議論する。 【スピーカー】
紹介文
紹介文
紹介文
紹介文
紹介文
紹介文
【モデレーター】
紹介文
|
|---|
| 20:00-20:15 | クロージング閉会の辞
|
|---|