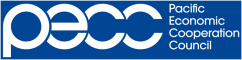 |
太平洋経済協力会議 ( PECC )
|
TOP | JANCPECの活動 | 今後のスケジュール | PECCとは | 機 構 | 活 動 | 成り立ち | 総 会
|
PECCとは
|
太平洋経済協力会議(Pacific Economic Cooperation Council, PECC)は産・官・学の三者により構成され、多様性に富んだアジア・太平洋地域の国際協力を推進するための組織である。
1978年、当時の大平正芳首相は、太平洋圏の将来性に着目し、この地域の協力関係強化が、単にこの地域のみならず世界経済の発展に役立つとして「環太平洋連帯構想」を打ち出した。 この構想の下、1980年9月にオーストラリアのキャンベラにおいて、11ヵ国(日本・米国・カナダ・豪州・ニュージーランド・韓国・ASEAN5ヵ国(当時))と太平洋島嶼諸国の代表による「環太平洋共同体セミナー」が開催され、今後の太平洋協力の進め方が話し合われ、これがPECCの前身となった。
現在、学界・官界・産業界の三者が個人の資格で自由な立場でアジア太平洋地域の国際協力を推進すべく諸活動を展開致しており、非政府組織としては唯一のAPEC公式オブザーバーとして、PECCの協力を求めるAPECに対し、情報、分析、提案などPECCの各タスク・フォースの研究成果を提供し、APECと有機的に連携している。
|
| ▲ページの先頭へ |
PECCの機構
|
PECCメンバー・委員会
【23加盟国・地域】
豪州・ブルネイ・カナダ・チリ・中国・香港・インドネシア・日本・韓国・マレーシア・メキシコ・モンゴル
ニュージーランド・太平洋島嶼諸国・ペルー・フィリピン・シンガポール・台北・タイ・米国・コロンビア
エクアドル・ヴィエトナム
【1準加盟】
フランス(太平洋地域)
【組織加盟】
PAFTAD (The Pacific Basin Economic Council)
PBEC (The Pacific Trade and Development (PAFTAD) Conference)
|
【常任委員会】
各メンバー委員会の代表者からなり、PECCの運営についての実質的な承認機関。
【執行委員会】
常任委員会の総意により承認された11名のメンバー。
|
【議長】
Mr. Jusuf Wanandi(Member, Board of Trustees, Centre for Strategic and International Studies (CSIS))
Mr. Donald Campbell (Distinguished Fellow, Asia Pacific Foundation of Canada and Senior Strategy Advisor, Davis LLP)
|
PECC活動の支援資金(中央基金)
PECCにおいては、総会開催については、ホスト・メンバーが、各タスク・フォース活動については幹事メンバーが、それぞれの必要資金を自発的に負担してきたが、PECC活動の活発化に伴い、特に途上国の委員会委員、学者等に対する活動資金援助の必要性が指摘されていた。こうした背景のもと、1988年5月の第6回PECC大阪総会において、当初3年間(1988年5月~1991年4月)に必要と予測される資金百万ドルをPECCメンバーが拠出することにより、中央基金が創設された。また、1992年以降も国際事務局の発足に伴い、加盟メンバーの毎年のPECC拠出が制度化され、この拠出を活用して、途上国/地域のPECC活動支援が継続されることとなった。
この活動支援は、従来、経済面での制約から会議への参加に支障を来していた途上国の学者等がPECC活動により広く参加することを可能にしており、PECC活動を一層充実させる上で、大きな役割を果たしてきている。
|
PECC国際事務局
1990年よりシンガポールに常設の事務局を設置。
国際事務局の必要経費は加盟メンバーの拠出金により運営。
国際事務局長: Mr. Eduardo Pedrosa
URL : http://www.pecc.org/
|
| ▲ページの先頭へ |
PECCの活動
|
具体的な協力活動は、PECCの下に設けられた個別分野毎のタスク・フォース、スタディーグループ等によって行われている。
State of the Region (SOTR)
幹事:PECC国際事務局
Social Resilience Project
幹事国:日本
Energy Transition and New Economic Models
幹事国:フランス(太平洋地域)
Regional Economic Integration-Review and Outlook
幹事国:台北
Global EPAs Research Consortium
幹事国:日本
|
| ▲ページの先頭へ |
PECCの成り立ちと総会
|
(注:名称・肩書きは当時のまま)
|
PECCが誕生するまで
(1)太平洋協力の構想は、第2次世界大戦以前より、関係各国の民間レベルの運動として継続的に展開されてきたが、戦後のヨーロッパにおける経済統合運動等に触発され、着実に構想の具体化が進められてきた。
特に、1965年小島清一橋大学教授が提唱した「太平洋自由貿易地域構想」はこうした動きに理論的根拠を与える重要なきっかけとなった。この構想は、太平洋地域にある先進5ヶ国(日本・米国・カナダ・豪州・ニュージーランド)を中心にして、太平洋に自由貿易地域をつくり、域内の関税をゼロに持っていこうとするものであった。この小島教授の構想を軸に1968年「太平洋貿易開発会議」(PAFTAD)が日・米・豪の経済学者を中心に発足した。
また、これと軌を一にして、財界においても太平洋地域への関心が高まり、日本商工会議所の永野重雄会頭(当時)が中心となって、先進5ヶ国の間で「太平洋経済委員会」(PBEC)が設立された。
(2) このように、初期における太平洋協力の展開は、日本が大きな役割を果たしていたが、主に学界・財界を中心とした活動であった。しかし、その後の日本経済の発展およびアジアにおけるNIEsの台頭は、太平洋圏における経済交流を活発化させ、同地域の重要性を飛躍的に増大させた。こうした中で、太平洋地域に対する関心はさらに高まり、国家レベルにおける太平洋協力の気運が生まれてきた。
1978年、大平正芳首相は、「環太平洋連帯研究グループ」を発足させ、「環太平洋連帯構想」を打ち出した。この構想は、世界の中で、最もダイナミックな発展・成長を遂げている諸国を包含する太平洋圏の将来性に着目し、政治・経済、文化の各方面において著しい多様性を持ったこの地域が、協力関係、相互依存関係を強めることで、単にこの地域,のみならず世界経済全体の発展に貢献することを目指している。
そして、同構想の特色として、次の三点を打ち出した。
a. 排他的地域主義をとらない。
b. 自由で開かれた相互依存関係を維持する。
c. 現存する二国間、あるいは多国間関係と矛盾せず、相互補完関係をなすものとする。
(3) 1960年代から1970年代における日本およびアジアNIEsの経済発展が、太平洋圏における経済交流の活発化、相互依存関係の深化を生むと同時に、様々な問題を顕在化させ、それらが上述のような太平洋諸国家間における協力の気運を盛り上がらせたわけであるが、その具体化にあたっては必ずしも平坦な道のりであったとはいえず、様々な紆余曲折があった。日本が提唱者となり太平洋の先進諸国が中心となった活動に対する東南アジア、ASEAN諸国の警戒心、および一部の国から出された反共ブロックの形成ではないかという非難などが存在したからである。しかしこのような状況にもかかわらず、太平洋協力活動は着実な発展を遂げていくことになる。また、米国の対太平洋貿易が対大西洋貿易を上回るという画期的な事態が生ずるに至り、「太平洋の時代」という認識が期待とともにさらに強まった。
|
キャンベラ・セミナー(第1回PECC総会)
太平洋協力の大きな流れの中で、1980年1月、大平首相は大来外相を伴い豪州を訪問し、フレーザー首相と懇談した。席上両首相は太平洋協力問題に関して広範なコンセンサスを得、太平洋協力構想を推進することで合意した。
この合意に基づき、1980年9月オーストラリアの首府キャンベラにおいて11ヶ国(日・米・加・豪・ニュージーランド・ASEAN5ヶ国及び韓国)と太平洋島嶼諸国の代表を集め「環太平洋共同体セミナー」が開催された。各国よりの参加は3名ずつで官界・財界・学界からそれぞれ1名ずつという三者構成であった。また、このセミナーには、アジア開発銀行、PBEC、PAFTADそれぞれの代表も参加した。
本セミナーにおいては、太平洋協力を今後進めていくにあたっての基本原理、形式などが話し合われたが、その中でその後のPECC活動の基本方針となる産・官・学三者構成の重要性が強調された。同時に常任委員会、複数のタスク・フォース設置が勧告された。
このキャンベラ・セミナーでは「環太平洋共同体」という名称が用いられたが、1982年6月にバンコクで開かれた会議で「太平洋経済協力会議」(PECC)という呼称が確立されるに及んで、同セミナーは、第1回PECC総会と呼ばれるようになった。
|
| ▲ページの先頭へ |
PECC総会
|
(注:名称・肩書きは当時のまま)
|
第21回PECC国際総会(バンクーバー、カナダ)
2013年6月3-5日に、カナダのバンクーバーにて、第21回PECC国際会議並びに2013年PECC常任委員会が開催された。PECC日本委員会からは野上JANCPEC委員長と畑佐研究員が参加した。今回のPECC総会は、Asia Pacific Foundation of Canadaが「Canada Asia 2013」という会議を主催するかたちで開催された。「Navigating Asia’s Future, Charting Canada’s Strategy」というテーマのもと、アジア太平洋地域の最新の経済動向、金融市場改革、技術革新、包括的成長、グリーン成長、サービス産業などの個別の議題についてディスカッションが行われたほか、カナダの本地域への貢献や関与のあり方にも焦点を当てた議論が交わされた。
PECC日本委員会としては、進行中のSRプロジェクトの中間報告を兼ねて、インドネシア、チリ、ミャンマーからの報告者を招いて、「Minding the Gap: Promoting Inclusive Growth and Resilient Society」と題するセッションを担当し、野上JANCPEC委員長が本セッションのチェアを務めた。また、常任委員会ではPECC日本委員会から、SRプロジェクトの継続と、「Global EPAs Research Consortium」という新規のInternational Projectの立ち上げを提案し、了承された。
PECC Vancouver Statementはこちら
第20回PECC国際総会(ワシントンDC、米国)
2011年9月28-30日に米国ワシントンDCにて、第20回PECC国際総会が開催された。今回の総会では、アジア太平洋地域の経済展望や地域協力のあり方を中心として、自由貿易協定の役割、エネルギー政策、雇用情勢、地域経済協力の行方などについて議論が交わされた。
また、コンカーレントセッションでは、サービス産業、TPP、Inclusive Growthという3つのテーマが設定され、それぞれ個別にディスカッションが行われた。PECC日本委員会はInclusive Growthのセッションを担当し、野上JANCPEC委員長がセッション・チェアを務めた他、SRプロジェクト主査であるチャールズ・ホリオカ大阪大学教授による、本プロジェクトの研究結果に関する報告も行われた。
常任委員会では、各メンバーエコノミーの活動状況や今後のプロジェクトに関して活発な議論が展開された。PECC日本委員会としては、昨年のSRプロジェクトの報告をすると共に、来年も引き続き本プロジェクトを継続することを提案し、常任委員会の了承を得た。今後のPECCプロジェクトの重要テーマとしては、エネルギーと財政の問題が挙げられ、引き続き関係者間で検討していくこととされた。
ワシントン総会の概要はこちら
ワシントン総会詳細はこちら
第19回PECC国際総会(東京、日本)
2010年10月20-22日にホテルオークラ東京にて、第19回PECC国際総会を開催した。日本でPECC国際総会が開催されたのは、1988年の第6回大阪総会以来22年振りのことである。また、今年はPECCにとって、1980年に第1回PECC会合がキャンベラで開催されてから、30年という大きな節目の年である。総会には、22ヶ国・地域のPECC委員会の委員をはじめ、各分野の専門家、有識者及び政府関係者等、延べ約300名が参加した。
「PECC30周年―APECの新たな展望と地域経済協力の更なる促進に向けて」“PECC at 30: New Vision for APEC and Toward Further Regional Economic Cooperation”というテーマのもと、アジア太平洋地域における新たな成長戦略のあり方や地域的課題について活発な議論が行われた。このPECC総会の模様はAPEC横浜会合にも報告され(PECC共同議長によるステートメント及び同添付の第19回総会報告書はこちら)、PECCとしても本国際総会の日本開催を通じで、APECの公式オブザーバーとしての役割を積極的に担うことができた。
第19回PECC国際総会プログラム
|
第18回PECC総会(ワシントン、米国)
2009年5月12日から13日の2日間、米国ワシントンD.C.ルネサンスメイフラワーホテルで開催された。PECC加盟メンバー委員会及び準加盟メンバーの委員長または代理が参加した(ブルネイ、フィリピン、ベトナムは不参加)。今回の総会(シンポジウム)のテーマは、「アジア太平洋地域における金融危機の影響とその回復」“Crisis and Recovery: Regional and Global Roles for Asia-Pacific Economies”で、昨年の金融危機に端を発した国際経済における影響をテーマに議論が行われた。米国アジア太平洋委員会、イースト・ウェストセンターの主催の下、総会参加者は、延べ300名を超えた。
日本からは、野上義二委員長、斎木尚子事務局長、平松賢司外務省経済局経済局審議官、塩田誠経済産業省通商政策局審議官、河合正弘アジア開発銀行研究所所長他12名が参加した。
総会に先立つ常任委員会においては、PECC日本委員会(JANCPEC)として「Social Resilienceタスクフォースプロジェクト(仮題)」の立ち上げ用意について野上JANCPEC委員長から発表した。Social Safety Net(年金、医療、高齢化問題、失業保険制度とその財源)、教育(およびその財源)についてのテーマでプロジェクトを2010年のAPEC日本開催に連動させて立ち上げるアイデアが報告された。プロジェクトの完了は2010年APEC日本開催までを予定。さらに、2010年に行われる次回第19回PECC総会を日本で開催したい旨、野上委員長が発言し、全会一致で承認された。総会(シンポジウム)の概要は次のようになる。アジア地域の景気低迷は、現在ほぼ底を打ったとする現状分析結果が多数報告された。その後の回復軌道については、V字回復するという主張やくしばらく乱高下を繰り返すという主張などいくつかに分かれた。全体として経済回復し持続的な成長を実現するためにも危機をチャンスとして、国内の構造改革に取り組む必要性や、自由貿易の利点を一時的な危機によって阻害しないよう過度の保護主義に陥る傾向を監視する必要性を主張する論調が多かった。また、経済危機回復もさることながら、地球環境問題においてもアジア地域が協調して既存の協調枠組みを利用するなどして取り組む必要性が改めて強調された。
ワシントン総会詳細はこちら
|
第17回PECC総会(シドニー、豪州)
2007年4月29日から5月2日の4日間、オーストラリアにて開催された。
荒義尚委員長、二階堂幸広事務局長、志野光子外務省経済局アジア太平洋経済協力室室長、高阪章大阪大学大学院教授、稲田義久甲南大学教授他日本からは11名が参加した。
シドニー総会詳細はこちら
|
第16回PECC総会(ソウル、韓国)
2005年9月6日より7日の2日間、韓国にて開催された。
荒義尚委員長、宮川眞喜雄事務局長、川口順子内閣総理大臣補佐官、柴田拓美野村アセットマネジメント株式会社執行役社長、小尾敏夫早稲田大学大学院教授、稲田義久甲南大学教授、地主敏樹神戸大学大学院教授他日本からは23名が参加した。
ソウル総会詳細はこちら
|
第15回PECC総会(ブルネイ・ダルサラム)
2003年9月1日より3日の3日間、ブルネイ・ダルサラムにて開催された。
佐藤行雄委員長、重家俊範事務局長、藤崎一郎外務省外務審議官、仁坂吉伸在ブルネイ日本大使、中東雅樹財務省財務総合政策研究所研究部研究官、鈴木均東京電力燃料部長、山澤逸平早稲田大学教授、菊池努青山学院大学教授、高阪章PEO構造問題TF主査・大阪大学教授他日本からは27名が参加した。
ブルネイ総会詳細はこちら
|
第14回PECC総会(香港)
2002年11月28日より30日の3日間、香港にて開催された。PECC議長のWilliam Fung中国香港PECC委員長が主催し、橋本龍太郎元総理をはじめ、董建華中国香港特別行政長官ら加盟25カ国・地域から産官学の知的リーダー及びWTO、OECDなどの国際機関の代表らが集まり、参加総数も約1000名と過去最大規模の総会となった。日本からは橋本元総理ら42名が参加した。
今次総会では「21世紀におけるグローバリゼーションの対応」というメインテーマの下に、貿易、金融、コーポレート・ガヴァナンスなど7つの全体会合及び10の分科会が開催された。議論の中心は、各分野でのグローバリゼーションヘの対処であり、様々な切り口でその光と影に関する論議が行われた。一部には市場主導のグローバリゼーションが進み過ぎ、国内政策を自立的に運営する国の主体的権利を確保する重要性を強調した意見もあったが、総体的には、開かれた地域主義を維持しながら、グローバル化に伴う課題を前向きなキャパシティ・ビルディングの構築などを通じて、如何に打開していくかという意見が大半を占めた。
松永日本委員会名誉委員長が進行役を務めた全体会合の第7セッションでは、橋本元総理より、太平洋地域におけるコミュニティの構築についてのスピーチが行なわれ、9月11日のテロ攻撃という世界に対する新たな挑戦に対し、国家の役割を再認識し、我々は正面よりこの挑戦を受けて立つべし、との強い意思が示され、さらにはグローバリゼーションに伴う数多い課題の中で、政府レベルだけでは解決できない国境を越える企業活動の分野に関し、産官学より構成されるPECCの役割が極めて重要であるとの主張がなされた。
さらに、中国、チャイニーズ・タイペイのWTO加盟については歓迎の意が表明され、この加盟自体がWTOを強化し得るとの期待の声があがると同時に、PECCおよびAPECが、WTOのニューラウンド交渉に如何に貢献すべきかというところまで議論が展開されたことが特筆される。
|
| ▲ページの先頭へ |
第13回PECC総会(マニラ・フィリピン)
1999年10月21日~23日の間、フィリピンのマニラで開催された。PECC加盟の22ケ国/地域・準加盟国フランス(南太平洋地域)をはじめ、主催国フィリピン大統領、ベネズエラの大統領の他、ラテン・アメリカ諸国、欧州、国際機関等より閣僚・閣僚経験者を含む約700名が参加した。日本からは、橋本前総理・内閣総理大臣外交最高顧問、松永日本委員長、新保経済企画庁審議官、藤井仙台市長、室伏伊藤忠商事会長、楠川富士総合研究所特別顧問、鈴木NTTコミュニケーションズ社長、高阪大阪大学教授、浦田早稲田大学教授ら37名、さらに現地日系企業から6名の計43名が参加した。
今回の総会においては、9月のAPEC首脳会議の結果を踏まえ、11月に行われるWTO閣僚会議の多角的貿易交渉への支援が念頭に置かれた。また、アジア経済金融危機の経験から、新しい国際経済構造への対応を模索するとともに、アジアにおけるデジタル経済についても議論された。さらに橋本前総理他はAPECの今後の有り様について様々な視点から提言を行った。採択されたマニラ宣言では、PECCによるこれまでのアジア太平洋地域の協力増進を評価するとともに、アジア経済危機の教訓を踏まえ、また経済や生活環境の急速な変容に応えていく必要性を認識し、引き続き産官学三者構成のユニークな組織に基づいた政策的指導力により、APECに対する重要な協力者としての役割を果たしていくとのコミットメントが確認された。
|
第12回PECC総会(サンチャゴ・チリ)
1997年9月30日~10月2日の間、チリのサンチャゴで開催された。PECC加盟の22ヶ国/地域、4月に準加盟を認められたフランス(南太平洋地域)をはじめ、ラテン・アメリカ諸国、国際機関等よりチリ、ブラジルの大統領・マレーシア首相、ラテン・アメリカ近隣各国の外務大臣、貿易担当大臣を含む約1,200名が参加し、これまでで最大規模のPECC総会となった。日本からは、松永委員長、奈良三菱総合研究所会長、室伏伊藤忠商事社長、原口外務審議官、塩飽農林水産省顧問、長富研究情報基金運営理事会議長、山澤一橋大学教授等46名が参加した。
ラテン・アメリカで初めて開催される総会となったため「トランスパシフィック・パートナーシップ:貿易・投資機会の実現に向けて」とのテーマのもとに開催された本総会では各種パネルや分科会において活発な討議がなされ、最終日にサンチャゴ宣言が採択された。同宣言では、トランスパシフィック・パートナーシップの推進のためのラテン・アメリカの役割の強化等が唱われている。
|
第11回PECC総会(北京・中国)
1995年9月27日~29日の間、中国の北京で開催された。新メンバーのベトナムを含むPECC加盟の22ヶ国/地域をはじめ、諸国・機関から約550名が参加した。日本からは、松永委員長、永井事務局長以下36名が参加した。
同総会では、「開かれた地域主義世界の繁栄を求めて」と題する北京宣言が採択された。同宣言においては、PECCのこれまでの実績およびアジア・太平洋モデルとしてのPECCの特殊性が認識され、貿易と投資の自由化と円滑化のためのAPECの役割に対する期待が表明され、さらに、PECCを通じて、アジア太平洋地域が世界的繁栄を促進し、21世紀の国際協力システムを形成するためのリ一ダーシップを発揮しうる旨述べられている。
|
第10回PECC総会(クアラルンプ一ル・マレーシア)
1994年3月22日~24日の間、マレーシアのクアラルンプールで開催された。新メンバーのコロンビアを含むPECC加盟の21ヶ国/地域をはじめ、諸国・機関から約550名が参加、うち日本からの参加は松永委員長、遠藤アジア太平洋協力担当特命全権大使以下37名であった。
「開かれた地域主義:更なる前進」のテーマの下に行われた本総会では、アジア太平洋地域での新しい環境の下でも、「産・官・学」の三者構成からなるPECCの広範な協力の枠組みは、ますます重要性を有するとの趣旨を明記した「クア
ラルンプール・コンコード(合意)」が採択された。
|
| ▲ページの先頭へ |
第9回PECC総会(サンフランシスコ・米国)
1992年9月23日~25日の間、米国サンフランシスコで開催された。新メンバーのロシアを含むPECC加盟の20ヶ国/地域、2国際機関をはじめ、諸国・機関から約550名が参加、うち日本からの参加は柿澤弘治外務政務次官、松永委員長以下、52名であった。
「開かれた地域主義:世界的経済協力のための太平洋モデル」のテーマの下に行われた本総会の最大の成果は、同テーマを副題とする「サンフランシスコ宣言」の採択である。本宣言では開かれた地域主義に対するPECCのコミットメントを謳い上げている。
|
第8回PECC総会(シンガポール)
1991年5月20日~22日の間、シンガポールで開催された。この総会から香港ならびにチリ、メキシコ、ペルーのラテン・アメリカ3ヶ国が正式参加を認められ、この総会で国際的に日本委員会委員長退任を表明した大来名誉委員長が歓迎演説を行った。総会参加者数体PECC加盟の19ケ国/地域、2国際機関の他、非メンバーの10ケ国、3国際機関からのゲスト参加も含め、358名であった。わが国からは大来名誉委員長、松永委員長以下、49名の代表団が参加した。
本総会では、PECCの目的、手続き、組織を規定したPECC憲章が採択され、機構的枠組みが整備された。
また、本総会より「人材育成」のタスク・フォースが加わり、PECCタスク・フォースは10となった。
|
第7回PECC総会(オークランド・ニュージーランド)
1989年11月12日~15日の間、ニュージーランドのオークランドで開催された。PECC加盟の15ヶ国/地域・2国際機関の他、非メンバーの13ヶ国、5国際機関からのゲストも含め、総勢364名の参加があった。日本からは大来委員長以下、44名の代表団が参加した。
特に本総会は、太平洋協力に対し、非常に関心が高まる中、11月6日~7日にオーストラリアのキャンベラで開催された第1回「アジア太平洋経済協力閣僚会議(APEC)」の直後でもあり、PECCとAPECとの関係が最も注目された。PECCの協力を求めるAPECのメッセージに応じ、PECCの独立性を保持しつつ、PECCの研究成果をAPECに提供することにより、政策決定に資するべきとの合意が得られた。
本総会ではまた、新たに「太平洋島嶼諸国」「科学技術」「運輸・通信・観光(Triple-T)」「熱帯林協力」の4つのタスク・フォースの設立が発表され、さらにPECCの国際常設事務局がシシガポールに設置されることも正式決定された。
|
第6回PECC総会(大阪・日本)
1988年5月17日~20日の間、大阪で開催された。この総会は、PECCの活動の提唱国であるわが国で初めて開かれたもので、PECC加盟の15ヶ国/地域、2国際機関の代表の他、16ヶ国、6国際機関からもオブザーバーが参加し、参加者総数は約860名と過去最大の規模となった。
この総会ではまた、ヴァンクーヴァー総会以降・活動を続けてきた六つのタスク・フォースの成果が発表された。この中で、前回総会で設置されて以来、わが国の主導で研究作業が進められてきた「太平洋経済展望」ワーキンググループは、太平洋域内諸国の経済分析および中、長期的展望に関する報告書「太平洋経済展望一調整とダイナミズム」を公表し、OECD経済展望の太平洋版として注目を集めた。また、次回のニュージーランド総会に向け10の諸活動を行うことを決定した。
本総会ではまた、PECC活動の実質的強化を目指して各メンバーが相応に拠出したPECC中央基金や「PECC組織強化」に関するタスク・フォースの設置が承認され、常設事務局の設置の可能性が話し合われるなど、PECCが将来一層発展するための重要な足がかりが形成された。
さらに、地元関西からは「環太平洋経営・技術交流促進機構」(のちに「太平洋人材交流センター」に改称)の設立提案が行われた。この機構は、太平洋地域の開発途上国の技術者、経営者を関西で養成することを目的としたものでPECC活動が従来の経済面の協力から社会面での協力ヘー歩踏み出すものとして満場の賛同を得た。
このように、大阪総会は、PECC活動が21世紀に向けて飛躍的発展を遂げるための画期的な総会として位置づけることができよう。
|
| ▲ページの先頭へ |
第5回PECC総会(ヴァンクーヴァー・カナダ)
1986年11月16日~19日の間カナダのヴァンクーヴアーで開催された。この総会には、従来のPECCの参加メンバーのほか、同総会で新たに正式参加を認められた中国、およびチャイニーズ・タイペイ(Chinese Taipei Committeeの名称で参加)からも代表が出席し、参加者の注目を集めた。さらに、若干の非メンバー国および国際機関からのオブザーバー参加も含め、参加者総数は160名を超えた。わが国からもPECC日本委員会委員長の大来佐武郎氏をはじめ、総勢32名が参加した。
本総会においては、前回ソウル総会で設置された四つのタスク・フォースと一つのスタディーグループの活動報告を受け、それに基づく活発な議論が展開され、基本的に五分野での活動を今後も継続していくことが合意された。但し、貿易政策タスク・フォースについては、既にウルグアイ・ラウンドが開始されたこともあり、より個別・具体的検討を進めるため、いくつかの小グループを設けることが提案され了承された。さらに、新規の活動として日本が提唱した「太平洋経済展望」プロジェクトにつき、日本の主導の下で研究作業を進めていくことが合意された。また、今後のPECC活動の指針とするため、日本委員会として、「太平洋経済協力の現状レヴュ一と展望」を行い、次回の大阪総会にバックグラウンド・ペ一パーとして提出することが承認された。
このほか、本総会の特に重要な成果としては「太平洋経済協力に関する声明(ヴァンクーヴァー声明)」の採択がある。同声明は過去6年間のPECC活動の実績をベースに、PECCの活動方針、目的、機構、具体的活動等を集大成し、明文化したもので、PECCの発展のための重要なワンステップとなった。
|
第4回PECC総会(ソウル・韓国)
1985年4月~5月に韓国のソウルで開催された。1984年1月にブルネイが独立し、その後ASEANに加盟したことから、PECCのメンバーも13(日・米・加・豪.ニュージーランド・韓・ASEAN加盟6ヶ国の計12ヶ国と太平洋島嶼諸国)となり、非メンバー、国際組織などからのオブザーバー参加も含め、約200名の参加者を集め、飛躍的な規模拡大が見られた。
このソウル総会は、たまたまボン・サミットの直前に開かれたこともあって、GATTの新ラウンドをめぐる議論が特に関心の的となり、次回のカナダ総会に向けて、四つのタスク・フォース(貿易政策、鉱産物・エネルギー、直接投資、漁業)と一つのスタディーグループ(畜産・飼料)において、さらに議論されることとなった。
|
第3回PECC総会(バリ・インドネシア)
1983年11月にインドネシアのバリ島で開催された。この総会には、メンバーおよびPAFTAD、PBEC、ASEANといった機関より60名の参加者と非メンバーおよびその他の組織から約50名のオブザーバーが参加した。
バリ総会では、バンコク総会で設置された四つのタスク・フォース活動の報告を受けるとともに、次回のソウル総会に向け、五つのタスク・フォース活動(前回のうち「工業製品の貿易」を「貿易交渉」に置き換え、「資本移動」を新規追加)を行うことを決定した。
また、組織の強化をはかるため、総会、常任委員会、タスク・フォース、調整グループ、各メンバー委員会という体制を整えることが決定され、いまだ委員会を持たないメンバーはそれを組織すること、また既に委員会を有するメンバーも、必要があればその組織をさらに強化することが合意された。
|
第2回PECC総会(バンコク・タイ)
キャンベラ・セミナー(第1回PECC総会)後も太平洋間の貿易の拡大、ASEAN諸国の順調な経済発展等により、太平洋協力に対する必要性の認識は更に高まり、特にASEAN諸国の中でもタイとインドネシアはPECCを積極的に評価するに至った。
そうした中で1982年6月バンコクにおいて第2回PECC総会が開催された。この総会には、12のメンバーおよびOECD、ESCAPなどの国際機関からオブザーバーを含め60名程が参加した。これらの参加者は、キャンベラ・セミナーと同様、産・官・学の三者構成をなし、それぞれ個人の資格による参加であった。
このバンコク総会の特色は、キャンベラ・セミナーの勧告に沿い常任委員会を設置したことで、太平洋協力における制度化の進展が見られたことと、同時に四つのタスク・フォース(鉱産物・エネルギー、貿易・投資と技術移転、工業製品の貿易、農産物と再生可能資源貿易)が設けられ、活動の具体化が進んだことである。
|
| ▲ページの先頭へ |

