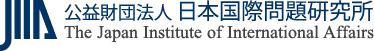「国問研戦略コメント」は、日本国際問題研究所の研究員等が執筆し、国際情勢上重要な案件について、コメントや政策と関連付けた分析をわかりやすくタイムリーに発信することを目的としています。
日本の国力としてのインテリジェンス強化
自民党と日本維新の会との連立政権樹立に際して発表された合意書12項目の中の一つに「インテリジェンスに関する国家機能の強化、総合的な改革」とあり、以下の施策について実行するとしている。
- 内閣情報調査室と内閣情報官を、「国家情報局」と「国家情報局長」に格上げし、国家安全保障局および同局長と同格とする。
- 内閣情報会議を発展的に解消し、「国家情報会議」を設置する。
- 2027年度末までに、対外情報庁を創設する。
- 省庁横断的な情報要員の養成機関を創設する。
- スパイ防止関連法制について検討し、法案を策定・成立させる。
情報(インテリジェンス)は国力の一部、国力を実際の影響力に転換する政治術・外交術(ステートクラフト)の一部である。日本の政治外交文化は歴史的・伝統的に情報を軽視してきたとも言われるが、近年、情報に関する国家機能は徐々に拡充されてきた。2013年に国家安全保障局を設置して政策サイドが集権化されたことも伴い、インテリジェンス・コミュニティの一体感も高まってきていると言われる。本稿では、新連立政権のこの合意について、若干の論点整理と課題抽出を行いたい。
第一に、内閣情報官(事務次官級)と内閣情報調査室を、「国家情報局長」(政務官級)と「国家情報局」に格上げすることは、それ自体はあまり実質的な意味を持たない。同格にしなくても、近年、国家安全保障局長と内閣情報官、国家安全保障局と内閣情報調査室とは緊密に連携していると評価されている。内閣情報調査室と比べて国家情報局の機能を実質的に強化するために、国家安全保障局・同局長に与えられているのと同様の情報アクセス権(他省庁に情報を提供させる権限、他省庁にとっては情報を提供する義務)を付与すべきとの意見がある。内閣情報官・「国家情報局長」に、総理の信頼と頻繁な面会機会がある人物が任じられれば、それが力の源泉となり、制度上の情報アクセス権がなくとも情報が集まるという面もあるが、アクセス権を付与されれば情報集約機能を制度的に担保するものとなろう。
ただし、仮に「国家情報局長」が情報アクセス権を得ることによって、「国家情報局」に集まる情報が内閣情報調査室時代と比べて質量ともに充実したとしても、「国家情報局長」一人では情報過多の洪水に溺れてしまう。かかる事態を回避するためには、現在内閣情報調査室に配属され「特定の地域または分野に関する特に高度な分析を担当」している内閣情報分析官の人数・任期・支援体制などを含め、集約・評価体制の拡充が必要だろう。
第二に、「対外情報庁」に関しては、たとえば、英国秘密情報部(MI6)や豪州秘密情報部(ASIS)のように、外務大臣の管轄下に外務省とは別組織として(公開情報や外交ルートでは入手できない)対外「秘密(シークレット)」情報の収集に特化した組織を創設するとの構想等がこれまで提起されている。世界においては、暗殺や政府転覆を含めて工作や諜報戦なども行う国もある中で、(そこまで日本がやることは想定されていないと思うが)日本として対外秘密情報の収集に限定するのか否か、国策や国家意思を相手国に飲ませるためにどこまでやるのか、という問題がある。日本の「国のありかた」にもかかわる。制度設計に際しては、そのような位置付けとして、検討される必要があろう。
第三に、内閣情報調査室は、公開されている組織図によると、国際部門で国外の分析のみならず情報収集も行っている。「国家情報局」が、情報の集約・分析評価・総理他へのブリーフを中心業務としながらも自ら情報収集をするのか否か、「対外情報庁」の情報収集業務との関係性を整理する必要があろう。人間は、分析評価を行う際に、自ら収集した情報を過大評価しがちになる。分析評価組織を収集組織と分離する意義の一つはここにある。豪州の国家情報庁(ONI)と秘密情報部(ASIS)のように、情報の分析・集約評価と収集を峻別している関係性が一つのあり方として示唆を与えうる。なお、現在、内閣情報調査室は対外情報と国内情報の両方を取り扱っているが、英米においては、対外情報を扱う組織と国内情報を扱う組織は分離されていることも付記しておく。
第四に、財政難と人口減少、すなわち限られた予算と人材の中での優先付けを考えざるを得ないだろう。情報収集分析手段は多岐にわたる。人的情報以外にも、情報収集衛星の位置付けの問題もある。商業衛星画像も入手でき、米国からも衛星画像が提供されるが、商業衛星画像との解像度の違い、シャッター・コントロールを持つか否かの違い、米国から情報が常に全て提供されることが保障されているわけではないことから、衛星画像では外国指導者の会話や心の内は読めないとの限界はあるが、日本が独自に保有している情報収集衛星の機能を拡充させる利点はある。また、近年、AIや自動翻訳機能の発達もあり、オンライン空間を中心とした公開情報の収集と分析の有用性が一段と増している。公開情報、サイバー空間情報、衛星情報、人的情報など、様々な手法の利点と限界とコストを勘案し、限られた予算と人員をどう再配分・再編するか、かつ、どう有機的に連関させて政策に役立つ質の高い成果物を生み出していくか、相当な熟議を要する問題だと思う。
最後に、今世紀に入り、内閣情報官の格上げや対外情報機関の設置を提言した「第一次・第二次町村レポート」をはじめ、インテリジェンス改革に関する多くの提言が発表されており、論点と難所は出揃っていると言える。インテリジェンス・コミュニティをどう改革するにせよ、少なくとも以下の二点が理解されることが重要であろう。
先ずは、全ての問題に関して、完全な理想形はなく、「インテリジェンスの失敗」も時には起きうること。一つの組織形態(特に、対外秘密情報機関)が軌道に乗り、質の高い成果物を生み出すには少なくとも数年以上の時間がかかること。従って、一内閣や一連立政権のみならず、長期的なタイムスパンでの超党派的な合意とコミットメントが必要であり、さらに国民への説明責任を果たすことで、国民の理解と支持が得られることが望ましい。
次に、良質のインテリジェンスが生きるか否かは、コミュニティの制度・運用・人材と同時に、それを活用する総理大臣をはじめとする政策決定者が、新設される「国家情報会議」への能動的な参画をはじめ適切な関心を払い時間を割くなど、政策側の問題意識と姿勢が肝要になる。自律的な外交安全保障政策を展開するためには、自律的な情報と情勢判断が必要となることは言うまでもない。
(以上)