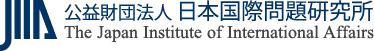米国ではここ数年、中国の戦略的な挑戦に対する懸念が高まっている。中国の対外的な自己主張――とりわけ海洋進出の促進や大経済圏の構築――が、アジア(ひいては世界)の勢力均衡や開放的な経済秩序を危うくし、また国際制度の有効性を脅かしかねないと受け取られているからである。米国の主導する国際秩序に対して、中国は「現状維持」を装いつつ、実際は「現状打破」を狙っていると見られるようになったのである。
トランプ政権の2年目に当たる2018年には、米国の対中警戒はいよいよ全般化、尖鋭化した。軍備拡張や経済進出に関する危惧が不公正な通商政策や不透明な借款提供――さらには国内統制の強化及び他国の統治攪乱――に纏わる懸念と直接に結び付けられたのである。前年末に発表された『国家安全保障戦略』は既に中国を「現状打破国家」と規定しており、2018年1月に要旨が公表された『国家防衛戦略』の中では中国は「戦略的競争者」と表現された。2018年10月のペンス副大統領による演説は、対中警戒の全般化、尖鋭化を最も纏まった形で示したものと言えた1。
中国の戦略的な挑戦が一段と深刻化しているとの認識を受けて、米国も次々と対抗的な措置を講じてきた。国防予算は大幅に増額され、南シナ海では「航行の自由作戦」が頻繁に実施された。インド太平洋の社会基盤整備に対する積極支援が打ち出され、台湾との関係強化も図られた。米国における中国の輿論工作への対応が進められ、中国の人権抑圧に対する制裁も検討された。
しかしながら、トランプ政権2年目の対中政策で最も耳目を集めたのは貿易面での攻勢であった。米国は2018年3月、知的財産権の侵害を理由に中国からの輸入品に標的を絞って制裁関税を課する方針を明らかにし、7月に340億ドル相当の中国製品に対して25%、8月に160億ドル相当に対して25%、9月には2000億ドル相当に対して当面10%(翌年初からは25%と予告)の関税が上乗せされた(中国も対抗措置を取った)。また、トランプは中国からの輸入品の中、残余の2670億ドル相当にも制裁関税を掛ける用意がある旨を表明した。
米国が中国との「貿易戦争」とも称せられる事態に敢えて突入した背景には、固より米国の対中貿易赤字が累増し、2017年には3700億ドル台にも上っていたという事実がある。また、米国内で貿易や産業を巡る中国の行動が著しく不公正だとの認識が強まっていることが、通商を巡るトランプ政権の対中態度への基本的な支持に繋がってきた。しかも、そのような認識は、中国が米国の技術覇権を脅かしつつあるとの危機感に結び付いている。
米国の見方によれば、中国は関税、為替操作、独自の基準、不透明な規制等を通じて自国市場を閉鎖し、補助金、減税、融資、政府調達等に関して国内企業を優遇している。また、中国に進出する外国企業に対して国内企業との合弁、保安審査(ソースコード等の開示を伴う)、データ現地保存、研究・開発施設設立等の要求を通じて技術移転を強要すると同時に、投資(合弁、買収、新規開拓投資)、学術交流(留学生の活用を含む)、研究・開発拠点設立、産業諜報、電脳窃取、人材勧誘を含む――一部は非合法な――各種の手段によって外国の知的財産を貪欲に吸収しようとしてきた。かくして中国は、外国技術への依存を低下させつつ、主要産業を代表するような自国企業(「ナショナル・チャンピオン」)を育成し、海外市場を席捲することを企てているというのである2。
そうした性格を有する中国の産業政策を織り込んだものとして、米国でしばしば槍玉に挙がってきたのが「中国製造2025」に他ならない。2015年6月に国務院によって全文が公表された「中国製造2025」は、次世代情報技術(第5世代通信規格〈5G〉を含む)、高級数値制御工作機械及びロボット工学、省エネ・新エネ自動車その他合計10の領域に力点を置きつつ、中国を「製造強国」として確立することを目指したものである。そこにおいては、中核となる部品や材料の中、自力で調達し得るものの比率を、全体として2020年までに40%、2025年までに70%に引き上げるとの数値目標が掲げられている3。
また、2015年10月には、特設された諮問委員会が「中国製造2025」の実現に向けた行程表(「路線図」)を発表した。「路線図」には、上記の10領域に入る製品、装置、設備の多くについて、国内市場または国際市場における占有率の具体的な目標が示されている。少数の例を挙げれば、移動端末チップは2020年に国内市場占有率35%、国際市場占有率15%、2025年に国内40%、国際20%、国産高性能計算機及びサーバーは2020年に国内60%超、国際30%、2025年に国内80%超、国際40%、産業用ロボットの国内市場占有率は2020年に50%、2025年に70%超といった具合である4。
米国通商代表部に言わせれば、「中国製造2025」は他国の産業支援と比べても「野心の水準」及び投入される「資源の規模」において際立っており、そこに盛り込まれた目標に到達するために中国政府が用いている政策手段は多くが「前例のない」ものであった。そして、仮に目標の達成が叶わなかったとしても、市場の歪みや過剰生産能力が生ずる公算が大きかった5。
トランプ政権は知的財産権の侵害を理由とする対中制裁の実施に際して、「中国製造2025」を標的にしていることを隠そうとしなかった。初めに追加関税の対象となった340億ドル相当、及び次に対象となった160億ドル相当の輸入品は、「『中国製造2025』計画に関係するものを含む、産業的に有意味な技術を組み込んだ」製品、或いは「『中国製造2025』という産業政策に寄与し、またはそれから利益を得る産業部門からの製品」と説明されたのである6。
「中国製造2025」に代表される中国の産業政策は、米国企業に対して中国市場における競争の困難や過剰生産を原因とする収益低下といった損害を齎しかねないだけではなかった。多くの先端産業において外国技術への依存を減らし、国産部品・製品の市場占有率を大幅に高めるという中国の計画は、総合的な技術力で米国を凌駕しようという意欲を表すものと判断せざるを得なかった。
実際のところ、近年における技術面での中国の前進は刮目に値する。中国は数年に亘って世界最速を誇った計算機を製造し、世界初の量子衛星を打ち上げ、米国を尻目に遺伝子組み換えを伴う臨床試験を実施した。研究・開発費の総額や国際特許の出願件数でも、中国は米国に迫っている。米中経済・安全保障再検討委員会(米国議会の諮問機関)は2017年の報告書で、先端技術を巡る両国の優劣を検討したが、それによれば超高速演算(次世代高性能計算機)、商業用小型無人機といった分野では中国が既に優位を占めている。また、生命工学、極微工学、クラウド演算、協働ロボットでは米国が優位を保つ一方、人工知能、量子情報科学、高性能演算では両国が拮抗しているというのである7。
但し、中国の技術水準を総合的に判定することは必ずしも容易でない。世界知的所有権機関(WIPO)等が発表した創新(イノベーション)に関する指標では世界第17位、世界経済フォーラムの競争力に関する指標では「全般」で世界第28位、「創新能力」で同24位に止まっているのである。米中経済・安全保障再検討委員会も、2016年の報告書においては、民間航空機、自動車、半導体を巡る中国の技術動向に厳しい評価を下していた。
何れにせよ、中国が技術力を向上させることは、米中間における軍事バランスの変化を急激に加速させる恐れがある。戦闘能力が民生技術の転用に依存する傾向が増大しているのみならず、例えば人工知能や量子技術に関連する特定の分野で中国が突破に成功することがあれば、長年に亘る米国の軍事的な優位が一気に覆されかねないからである。
そこで、米国は、非合法な手段を通じてでも技術情報を取得しようとする中国の動きを阻止する取り組みに本腰を入れるようになった。知的財産権の侵害に対する制裁関税の賦課を巡っては、当然ながら中国に進出した企業に対する技術移転の強要が――「経済的でない方法」による米国での技術購入及び電脳窃取ともども――その理由として挙げられており8、また中国からの投資制限や「強化された輸出管理」のための方策を併せて策定する方針が示されていた9。
2018年8月には、外国投資リスク審査近代化法(FIRRMA)及び輸出管理改革法(ECRA)が成立した。FIRRMAは外国からの投資の安全保障への影響を検討する対米外国投資委員会(CFIUS)の権限を強化するものである。それによって、中国企業による米国企業との合弁やその買収等に対する審査の幅が広がることになった。一方、輸出管理は技術ではなく製品を焦点としてきたが、ECRAは「新興技術」及び「基盤技術」を対象として輸出規制の体制を構築しようとするものである。それに基づき、商務省は既に14分野の新興技術について、どのような輸出規制が必要かの検討を始めている。
また、大学を通じた技術流出を防止すべく、国務省はロボット工学、航空工学等を専攻する中国人留学生に発給される査証の有効期間を短縮した。中国軍と関係の深い多くの中国企業が新たに輸出規制の対象に指定され、また技術情報の盗用(電脳窃取を含む)が相次いで摘発された。
さらに、米国の政府機関による中国の通信機器大手ZTE(中興通訊)及び華為技術(ファーウェイ)の機器やサービスの利用が法律で禁止された10。これらの企業を巡っては、その製品に特殊な仕掛けが施され、情報が抜き取られて中国政府に提供されたり、有事に際して米国の社会基盤を攻撃するのに使われたりすることが懸念されるというのである。そうした懸念のため、米国は中国で製造された情報通信機器を一様に「5G調達から排除する可能性が極めて高い」と言われる11。
さらに、貿易、技術に関する米国の対中政策は、同盟国等をも直接に巻き込むものとなった。北米自由貿易協定(NAFTA)の改定交渉を経て、2018年9月には米墨加協定(USMCA)が合意を見たが、そこには「非市場経済国」――当然、中国を含む――との自由貿易協定(FTA)締結を牽制する文言が盛り込まれていた。また、米国は日本、ドイツその他に対して、華為技術の製品を使用しないよう求めるに至った。
米中間の貿易摩擦は2018 年12 月のトランプ=習近平会談で「一時休戦」を見た。両国は新たな貿易協議の開始で合意し、当面する90 日間は2000 億ドル相当の輸入品に対する米国の制裁関税は10%で据え置かれることとなったのである(翌年2月に据え置き期間は延長された)。
「貿易戦争」の行方如何に関わらず、米中の戦略関係に関して見落としてならないことの一つは、米国を主軸とする国際秩序に対して中国が「現状打破」を図っているという構図の説得力にやや翳りが見られることである。それは、米国が在来の国際制度から離れようとする傾向を強めたため、中国が――秩序改変への志向を覗かせながらも――「現状維持」を事とするかの如く振る舞うことが、より容易となっているからに他ならない。
国際制度に対するトランプ政権の姿勢は、2018 年9 月の国連総会における大統領の演説でも明瞭に示された。「グローバリズムのイデオロギーを拒絶する」旨が明言されたのである12。これに対し、同じく国連総会で演説した中国の王毅外相は「我々は一貫して国際秩序の擁護者及び多国間主義の実践者である」と主張した13。また、習近平国家主席も同年12 月、中国は「国際秩序の擁護者となった」と述べたのである14。
2 国内、海外での技術取得の手法に焦点を据えて、中国の産業政策に分析、批判を加えた政府機関の文書に、Michael Brown and Pavneet Singh, China’s Technology Transfer Strategy: How Chinese Investments in Emerging Technology Enable a Strategic Competitor to Access Crown Jewels of U.S. Innovation, Defense Innovation Unit Experimental (DIUx), January 2018及びWhite House Office of Trade and Manufacturing Policy, How China’s Economic Aggression Threatens the Technologies and Intellectual Property of the United States and the World, June 2018がある。
3 国务院『「中国制造2025」(全文)』2015年5月8日。該目標は8-9页を参照。
4 国家制造强国建设战略咨询委员会『「中国制造2025」重点领域技术路线图』2015年10月。該目標は7-8,35-36页を参照。
5 United States Trade Representative, 2017 Report to Congress on China’s WTO Compliance, January 2018, p. 10.
6 “Statement on Steps to Protect Domestic Technology and Intellectual Property from China’s Discriminatory and Burdensome Trade Practices,” May 29, 2018, https://www.whitehouse.gov; United States Trade Representative, “USTR Issues Tariffs on Chinese Products in Response to Unfair Trade Practices,” June 15, 2018, https://ustr.gov.
7 U.S.-China Economic and Security Review Commission, 2017 Report to Congress, November 2017, ch. 4. 米中比較の一覧はp. 532を参照。人工知能に関連して言えば、自動運転車では米国企業が、言語認識及び合成音声では中国企業がそれぞれ主導しつつあると言う(p. 527)。
8 “Remarks by President Trump at Signing of a Presidential Memorandum Targeting China’s Economic Aggression,” March 22, 2018, https://www.whitehouse.gov. 引用された科白はライトハイザー通商代表によるものである。
9 “Statement on Steps to Protect Domestic Technology and Intellectual Property.”(註6)
10 なお、ZTEに関しては、イラン及び北朝鮮への輸出に関連して2018年4月に米国企業との取引が禁ぜられていたが、罰金支払い、経営陣交替等と引き換えに、その制裁は7月に解除された。
11 國分俊史「“実害”なくとも中国企業は排除――背後の共産党を恐れる米豪」『ウェッジ』平成31年1月号、19頁。
12 “Remarks by President Trump to the 73rd Session of the United Nations General Assembly / New York, NY,” September 25, 2018, https://www.whitehouse.gov.
13 「王毅在第73届联合国大会一般性辩论上的讲话(全文)」2018年9月28日,新华网。
14 「习近平:在庆祝改革开放40周年大会上讲话」2018年12月18日,新华网。